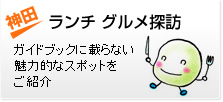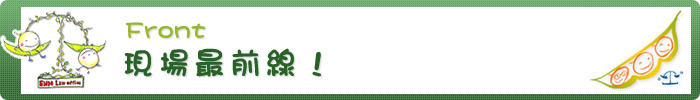 現場最前線
現場最前線
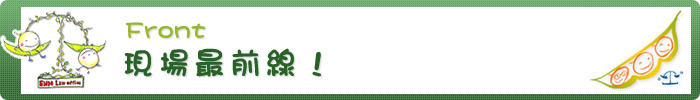
家族法が変わる、共同親権だけじゃない。改正法の5つのポイント。
近年、家族の形が多様化する中で、法律のあり方も見直されつつあります。
2024年に成立した改正民法では、ニュースでも話題になった「共同親権の導入」以外にも、私たちの暮らしに関わる重要なルールが大きく変わることになりました。
本稿では、2026年4月までに段階的に施行される予定の「家族法改正」について、一般の方にもわかりやすく解説いたします。
1つ目のポイント 親の責任が明記された
これまでは、親が子どもに対してどのように向き合うべきか、法律上は明確な規定がありませんでした。
今回の改正により、次のような「親の責任」が初めて法律に書き込まれました。
- 子どもの人格を尊重して育てること
- 子どもの利益のために、父母が協力すること
離婚や別居など家族のかたちに関係なく、親が子どもにしっかりと向き合う責任があることが、よりはっきりと示されました。
2つ目のポイント 養育費の確保が手厚くなった
離婚後、養育費が支払われないままになるケースは少なくありません。
そうした事態に備えて、以下のような仕組みが整備されました。
- 「法定養育費制度」の新設:養育費の取り決めがなくても、最低限の生活費を請求できるようになります
- 養育費に「先取特権」が付与:養育費の支払いが滞った場合、差押えがよりスムーズに行えます
- 収入や資産の情報開示が簡素化:相手方の財産状況を把握しやすくなります
これにより、養育費に関する不安が少しでも軽減されることが期待されます。
3つ目のポイント 面会交流のルールが明確になった
これまでは、親子の面会については明確なルールがなく、トラブルの原因になることもありました。
改正法では、以下の点が定められました。
- 離婚前の別居中でも、親子の交流が可能であることを明文化
- 裁判所による「試行的な面会交流」の導入
- 場合によっては、祖父母など親族による面会請求も認められるようになります
子どもにとって必要な人間関係を保つ仕組みが、より法律で保障される方向に進んでいます。
4つ目のポイント 財産分与のルールが明確になった
離婚後の財産分与についても、当事者がより公平に分け合えるようルールが整備されました。
- 請求できる期間が「離婚後2年以内」から「5年以内」へ延長
- 家庭裁判所が考慮すべき判断要素が明文化(婚姻期間・貢献度など)
これにより、時間的なゆとりをもって話し合いや調停を進めることができます。
5つ目のポイント 養子縁組のルールが明確になった
複数回の養子縁組がある場合や、親の同意が得られないケースについても、家庭裁判所の判断により対応できるようになります。
これにより、子どもの福祉が最優先される制度設計がなされました。
今回の法改正では、一貫して「子どもの利益を最優先にする」という考え方が貫かれています。親の権利や都合ではなく、子どもが健やかに成長するために必要な環境を、法律が後押ししていく それがこの改正の大きな方向性です。
当事務所では、離婚、親権、養育費、面会交流など、家族に関する法的なお悩みに幅広く対応しております。